| 佐藤義雄さん(日立市在住)が綴られてきた侵略戦争を 告発する9冊のパンフレットのなかから、一つを転載します。 |
||
|
戦中・戦後をかえりみて -- 侵略戦争正当化脱却のために |
 |
|
佐藤 義雄 |
||
| 憲法改悪反対!! 憲法九条は日本と世界の宝である |
||
|
目次 |
|
|
|
|
|
|
はじめにふりかえってみると私が戦争体験記を『文化評論』(現在は廃刊)に応募したのは二一年前になります。現在読んでみて分かることは、私自身が加害者だったことにはふれてないことです。それまでの私は、自分が参加した日中戦争が侵略戦争だったことを認識するようになって、それを証言するための戦争体験手記だったのですが、そうしたなかで自分自身の位置はどうだったのかと言うことが空白だったと言うことは、侵略戦争への切実な反省点に欠けていた現れだったのです。日本の歴代政府は侵略戦争を否定し、中曽根内閣が「皇位六〇年祝賀式典」行事を行ったのは一九八六年で、この年に私は帰省の機会があり、はじめて生まれ故郷の戦没者墓碑を訪れ廻ったのですが、この時から自分の戦争体験と向き合うようになったのです。 それから二〇年、現在では憲法改悪阻止闘争が重要課題となった情勢のなかで、戦中と戦後の時代に生き、晩生を残すのみとなった一人として、感じたまま、心に留ったことの若干を記すことにしました。 第一章 侵略戦争拡大のなかで(1)「満州事変」をかえりみて私の小学生時代は一九二六年(大正十五)から一九三四年(昭和九)の八年間になります。この間を歴史年表で見るといろいろな事のあったことが記されていて私なりに思い出される記憶もあります。そうしたなかで最も大きな出来事として記憶に残っているのは、一九三一年(昭和六)九月十八日に起きたいわゆる「満州事変」であったと言えます。小学六年生でしたし、はじめて経験する日本の戦争であり私の町からも戦死者があったからです。この満州事変をどんな経路で知ったのかはおぼえがありませんが、ニュース映画で日本軍が北大営の中国軍を砲撃しているのを見て胸をわくくさしてよろこんだことは、これはいまでもはっきりとおぼえています。これは小学生だった私のみでなく、当時の国民大多数の姿だったのだろうと思います。日本関東軍参謀の謀略による鉄道爆破を中国軍の行為とする軍部や政府の嘘の宣伝を真にうけていたわけです。いま考えると、この状態にはすでに国家の滅亡寸前にまでも進んだ太平洋戦争への道に通ずる姿があったと言えます。 何故かと言うと、戦争の主力となった太平洋での戦局が困難から後退に変わるなかで、何回も行われた「大本営発表」を信じて戦争協力をつづけた大多数の国民を思い出すからです。ポツダム宣言の六項のところには、日本国民は戦争を犯した権力・勢力に欺かれたとありますが、すでに「満州事変」で歴史の事実はこのことを示していたからです。 ポツダム宣言を読むのは復員後ですが、すでに私は戦地で「聖戦」宣伝は真っ赤な嘘と分かりましたし、欺かれていたのはその通りと思いました。しかし自分や国民大多数が何故欺かれたのかと言うことは、問題意識として深く考えたことはなかったのです。戦後に自分の戦争体験と向き合う中で、歴史書物もあさったりして学んだことは多くありますが、いま私自身をふりかえって言えることは、「万世一系の天皇」を中心とした明治政府成立以来の日本国家が歩んだ歴史と、そのなかで強調されていった皇国史観の役割に気付いた事です。このことを経験的に言えば小学生時代の教育勅語が思い出されます。驚いた事には世紀が変わった今日でも「日本は天皇中心の神の国である」と発言した人物が総理大臣にも居たことです。 アジア諸国からの批判の中で続けられている小泉首相の靖国参拝と前回の総選挙の結果は或る種の排外主義的なナショナリズムの台頭の可能性すら浮かばせます。「満州事変」前後時期の日本はそうだったからです。 国民が欺かれるのは国民の多数が欺かれているのを知らないからで、アジア・太平洋戦争と言う過去の歴史に学ぶことは重要なことです。 (2)日中戦争全面化と私の反省小学校高等科を卒業した翌年に日立市内のセメント会社に就職し叔父(義理)夫婦のところに住むようになったのは十五歳のときでした。その翌年に起きた軍事クーデターである二・二六事件のことは、夜勤で職場に行ったら「東京はつぶれたそうだ」との話しを耳にし、事情は不明だが驚いたので記憶していますが、まだ少年期でもあったからか強い関心もないままにすぎています。しかしこの事件以後、政治面での軍部の力は強化され軍国主義強化のテコとなったと言うことを戦後知識で知りましたが、当時はこのクーデターを私は愛国心の結果として見ていたのですから、何となく軍国路線の風潮に影響されていたものと思います。この二・二六事件の翌年の一九三七年(昭和十二)七月七日に蘆溝橋事件が起き、これが発端で日中戦争全面化となるわけですが私は十七歳になっていたのにこの事件の記憶は漠然としか残ってないのです。それは中国でのことは身近に感じていなかったからでしょう。ところが二年前にはすでに日本共産党の指導部は壊滅させられ、国民への思想統制は日常的にも強化されていたのです。その現れが、左翼文学好きだった私の職場の先輩青年が或る日警察に呼び出されると言うことがあったのでした。その先輩と仲良かった私までが職場長から「余り仲良くするな」と言われたりしたのです。何となく意味は分かる程度でしたが先輩はさけました。 そんなことがあってからですが、間もなく日中戦争が全面化されると召集令状が近所の青年に来たり、職場の先輩達も召集されるなど不安の拡がる中でやがて叔父も召集されるなど戦争は身近なものとなり、町内からは戦死者も出たのです。 こうしたなかで私は、この戦争が日本による中国への侵略戦争との考えは全くなかったが、戦争には心情的な思いながら反対の気持でした。しかし戦後になり戦争体験と向き合うなかで、当時の私の日中戦争への態度には重大な問題があったのに気づいたのです。それは侵略戦争拡大のための法律であった国家総動員法が国会で審議されていることや成立、公布されたことにも全く無知で無関心だったと言うことです。 私が自分としては好まなかった陸軍造兵廠に就職するようになったり、漁師の実兄が南方に漁船と一緒に徴用されたり、故郷の住民を含め一三五名が軍命令で漁労中に米軍機に射殺された鹿島灘沖事件などは国家総動員法による法令のためだったのを知ったのは戦後です。私が新ガイドラインによる有事法体制に反対して、住んでいる団地で署名活動をやったのはこの国家総動員法の経験があったためもありましたが、当時は政治と戦争の関係について無知・無関心だったのです。これは戦後に戦争体験と向き合ったなかでの一つの教訓でありました。 (3)軍国主義の高まる中で侵略戦争を拡大してゆくためには国民の協力が不可欠であり、支配層は戦争は「東洋平和」確立のための「聖戦」であると大宣伝をしました。それは新聞などで知っていましたが、その宣伝の内容に「反共主義」が使用されていたのを実際に知ったのは戦後に入手した戦時中の一冊の出版本からです(巻末資料を参照のこと)。ここには「聖戦」宣伝の一つの特徴があったのですが、当時の私にはその事実すら知らずにいたのです。あの戦争拡大に国民を協力させるために「反共主義」が使用されたと言う歴史的事実は、あの戦争の本質・性格を知る上で重要な一面であると思いますが、私はそれをも知らずにいたわけです。しかしそれでも前述したように、日中戦争全面化する当初の時期には、心情的ではあったが戦争には反対であったことは、これまで作った小型パンフの戦争体験手記にも述べた通りです。ところが一九三八年(昭和十三)の漢口攻略戦開始の頃から戦争支持に変わっていったのです。いまその頃のことを考えますと、軍国主義潮流が高揚し全国を包んだと言う背景があり、反面左翼陣営も弾圧下で後退が強まって一般国民の前から見えなくなっていて、私なども宮本百合子の名前すら思い出さなくなっていたのですが、左翼陣営への弾圧があったことすらその頃には知らぬままにいたのです。だからその頃人生問題から関心を持った唯物論の本などで名前を知っていた戸坂潤などの唯物論研究会が強圧下で解散したなどのことも知りませんでした。いま考えると実際の現実社会がどう動いているのかと言うことへの関心はなかったわけで、身のまわりの召集令状や出征など、戦争がもたらす生活への犠牲から戦争反対の気持だったのです。それ自体は大切なことだったとは今も思いますが、そうした心情的反対のみでは権力の進める戦争路線を本質的にはとらえ切れずその潮流に流されていることも気づかずに生活していたのではなかったかと思います。 そう思って今日現在の若い人達を見ると、戦争経験を全く知らないだけに、私など以上に戦争問題と政治問題への関係などについては無関心に近いのは実状なのではないかと思いますが、憲法改悪、九条の危機に直面していることを思うと大事な問題です。 しかし私達の若い時代と大きく違っていることも事実です。有事法体制反対のビラを団地などで戸別に入れた時など、話しをするとビラを真剣な顔で読み、私に頭を下げて礼をのべた青年を見て、過去の時代との違いを知った思いをしたことがあったからです。ビラと同時に、話すことの自由や権利の拡大の違いもあるなかでの今日の青年である事です。 漢口攻略戦の頃十八歳だった私は、青春初期としての人生問題で内向的傾向がつよまる年頃であり、私の戦争態度も変化があったのです。日中戦争全面化当初にはあった町内や職場から召集令状で戦地に持ってゆかれた人達や家族などへの思いやる気持は消え、戦争は国の問題であって自分でどうなる問題でもないし、自分は自分の人生問題を考えればいいんだと言う考えになっていたのです。それではその自分の人生問題とは何かと言うと「罪の意識」問題でその解決に悩んでいたのです。 ここに大きな変化と言うか誤りがあり、戦争と自分の人生問題、生き方の問題は別問題だと断ち切ってしまっていたのです。それは国家総動員法に無知・無関心であったと言う政治と戦争への問題点よりもさらに深く人間と戦争の関係についての態度で問題点を持つようになっていたのです。それは一つの罪悪とさえ言えることだと今は思います。何故なら人間の尊厳を踏みにじった兵士としての自分の原型のようなものをそこに感じられることと重なるからです。 当時の私は自分の「罪の意識」に向き合って悩むようになっていて、この「罪の意識」からの脱出と再生への道を求めて歩んでいた文学評論家の亀井勝一郎の著書を熱心に追っていたのです。そして亀井氏なども同人である『文学界』を手にしたなかで、一九三八年(昭和十三)六月号でかつて左翼文学好きの先輩から名前はきいて知っていた作家の島木健作の聖戦論を知り、急に目の前が開けたような共鳴感にとらわれたのです。これが「聖戦」としての戦争観を持つ発端でした。そして島木氏の小説『生活の探究』を読んで感銘し「聖戦」を信じるようになりました。 以上が日中全面戦争が進展していた頃の一青年である私の戦争に対するかかわりでした。終戦翌年に復員して間もなく知った事ですが、私の戦争への「聖戦」観を導いた島木健作も、これを強めた亀井勝一郎も二人共転向文学者だったのです。二人の影響を受けた時期はそうした時期であり私は日本共産党など反戦陣営への弾圧もほぼ終わった戦争拡大の時代の青年だったのです。当時の私は前述の文学・文芸誌『文学界』紙上で「転向」と言う言葉に接したことはありましたがその意味する事については殆ど理解しないままにすぎていたのです。 (4)「聖戦」崩壊と兵士への影響私が軍隊の召集令状を受けたのは一九四二年(昭和十七)七月で十月はじめには中国湖北省内に居た現地部隊に到着しています。召集を受けてから私の戦争への態度は自己自身として形成されました。それは戦場での死と言う問題です。それをどう受入れるかで、私は「聖戦」の戦場で死に直面した場合に、その死を「無償の行為」として受取れたらその死も、自分の人生も立派なものと言えるのではないかと思ったのです。「無償の行為」としての「死」の受容と言うこの観念思想は、後日気づきましたが亀井勝一郎の影響だったのですが、これが私の出征態度だったのです。そしてその態度を守るために『防人の歌』と言う一冊の本を持って入隊したのでした(この本は当時の出版です)。 このことはこれまでの何冊かの手記パンフでも述べたことがありましたが、六〇余年をすぎてふり返ると軍国主義と戦争の犠牲となった青年の姿が浮かんできます。死の中にしか生きることを描けなかったと言うあの侵略戦争時代の青年のことです。こうして現実の戦場を実際に知らない私は「死」を自己自身で美化しながら出征したのです。そして生還しています。しかし死以外にはない出撃特攻隊員は「悠久の大義に生きる」ためとして若い命を終わらしていったのを思うとたまらない気持になります。 聖戦と信じ自ら戦死をも美化して兵士となった私は、入隊直後に経験した天皇の名による無茶な私的制裁にも内心での反抗感も持たず、一般軍務にも熱心だったと言える兵士だったのが変わったのは、入隊七ヶ月に参加した初めての軍戦闘作戦を体験したことが大きな原因です。その作戦を通じて日本軍の戦争が中国住民の食糧はもとより家財道具までも略奪・破壊することで成立し一体のものだったことをはじめて分かったからです。戦後知識で分かったが、中国での戦争では「現地調達」が軍正規の方針だったので後方補給を軽視しており、特に食糧については中国では現地でぶん取れると軍中央も考え後方補給はなかったのです。軍隊が日々戦場で必要な食糧や食事用具類(薪とか鍋など)は最小限必要でこの確保のための「徴発」は不可欠の作戦行動の一つだったのだと分かってからは、当初は中国住民への気がねなどもありましたが、その後は正当行為感で徴発には一種の解放感すら抱くようになったのです。私はこの現実が戦争と言うものだったのだと分かり、自分の戦争認識を改めたものの、まだ「聖戦」なのだと思っていたのです。作戦行動の日々の連続で初年兵ではじめての作戦参加であり余計なことを意識する余裕などはありませんでした。 この時の作戦参加体験は手記のパンフでも記したので省略しますが、この実際の戦争体験が、私の兵士像を一八〇度変えることになったのは、作戦が終了し部隊警備地にもどってから何日かすぎた或る日のことです。 その日内地の親しかった友人から便りがあったのです。この友人は私に左翼作家やその小説などを語ったこともあった友人でしたが、その便りには大東亜共栄圏のため大東塾と言う右翼団体に通っているとあったのを知りびっくりしたのです。そしてその反動反射で終わって間もない参加作戦を思い出し、この時に日本の戦争目的理念と実際の日本軍の戦争行為との矛盾に気づき、「聖戦」は真っ赤な嘘で自分も国民も欺かされていたと分かったのです。 これは「聖戦」を信じて『防人の歌』一冊を持ってきた私にとり大きなショックでした。そして一体この戦争は何のための戦争なのだろうかとの疑問も生まれたが、それは私には分からない事で疑問はすぐ消えたのです。戦後になって気づいたのですが、警備地では毎朝のように軍人五ヶ条を唱えさせられてきたのに、戦争への疑問が頭を走ったときに天皇の事は全く意識上に浮かばなかったことです。それは小学生から天皇神性化に馴らされていた結果だったと思いますが、いまかえりみて「聖戦」に欺かれた大元の根はこうしたところにあったようにも思います。一、二日後私は『防人の歌』を投げ捨てましたしこの時「無償の行為」の観念も消えたのでした。 こうしたなかで私には自分だけで分かる内面の変化が生まれていました。一つは軍隊の差別的階級制への不満です。いま一つは何時命がなくなるか分からぬ境遇であり乍らそれから逃げることの出来ない身であることからの自暴自棄的心境です。 そんな或る日のこと同年兵の一人が、衛兵所勤務中に部隊倉庫から持ってきたと言って白砂糖をくれたのです。つまり夜の動哨中に倉庫から盗んできた砂糖なわけで驚きましたが、私は同年兵を責める気持はなく、そんなことが出来るなら自分もとその時思ったのでした。 私が衛兵所勤務時に部隊倉庫の扉が開いていたのをよいことに内の砂糖を盗んでいるのを経理部の兵士に見つかったのはそれから何日かすぎた或る日のことです。勤務終了後衛兵長だった古参兵にビンタをとられたが、部隊公表にはならずに、この事から間もなく中隊本部から分遣隊に勤務替されて終わったのです。 後日知ったことですが、当時部隊倉庫の砂糖が無くなることから、中国人の仕業と思い倉庫の扉を開けておいて監視していたとのことです。犯人は中国人どころか規律違反も重大な部隊衛兵所勤務兵だったのです。このことが分かり部隊幹部は上部からの責任追求をおそれ私の事は伏せて公表しなかったものと思います。分遣隊勤務で終わらしたのです。 私がこのことを記すのは、一部隊のこの出来事の中に皇軍と言われた旧日本軍隊の根深い内部矛盾の現れを見る思いがあるからです。日本軍隊の規律の大元は明治天皇が軍人に下した軍人勅諭であるが、それは兵士の人権を無視した非近代性の抑圧であり、兵士民衆自らの要求とは矛盾していたのです。「馬より安い一銭五厘」と扱われた兵士の不満や反抗が戦地と言う強制の中で現れるのは当然であったのです。そうした自覚的認識はないまでも、すでに同年兵に先行者はあったことであり、部隊公表もなかったし、私自身は監視体制中とは知らずに行動した自分の不運とへまを悔んだのみで、軍隊の規律違反でも悪事をしたとの意識はなかったのです。 第二章 「帝国軍」一兵士の終末(1)作戦出動兵士の合唱と輪姦分遣隊の兵士間に近く何処まで行くのか先の分からぬ大作戦があるそうだとの噂が流れたのは一九四四年(昭和十九)三月頃です。そしてくわしい事は分からないが全員出動開始したのは四月でした。これは戦後知識によりますが、この時期は戦局の主力である南方戦線の後退がつづき、七月のサイパン島陥落なども間近になる頃ですが、そうした戦局は兵士には何にも分からないながら、今度の作戦がこれまで経験したものとは違うことは出動体制で兵士にも感じられたのです。大作戦ありの噂が流れた時私が思った最初のことは、これまでは無事だった命の有無への不安感で、今度は危ないのではとも思ったのです。これは兵隊誰もが思ったことだったと思います。このことで忘れられないのは、警備地だった処から出動した日の夜行軍中に、故郷を想う言葉のある歌で、兵隊にも流行した「伊那の勘太郎」を誰かが歌い出すや全員に合唱されたことです。私も家族や故郷を心に浮かべながら歌仲間に入ったのでした。 これも戦後知識ですが、三五万の兵力が動員され、直線距離一千五百キロ、期間は七ヶ月を費やした大作戦で、通常名称は湘桂作戦と呼ばれています。中国大都会の漢口から揚子江を渡河し、私達の師団は当時の広西省奥地をすぎ貴州省独山まで侵攻したのです。 何回目かの作戦参加で、気づかぬことながら兵隊の気持は動揺し不安定化していたと言えます。それは漢口郊外に数日間居た或る日、仲間三人と郊外散策に出掛けた時、三人で農家に入り一人居た女性を輪姦し、分からなければやり得と、一片の罪の意識もなく平然と部隊に帰ったからです。 この時私は敵国の女をどうしようと法の罪には当たるまいと言う誤った考えに自分を導いたのですが、いま一つには今度の作戦で命がどうなるかは分からないのだと言う自暴自棄もあったことです。かえり見て思うことは人権思想は一片もなかったことです。「人権」と言う言葉すら知りませんでしたが、私と言う人間性そのものの荒廃が進んでいたのです。そしてそれは、中国侵略戦争の一側面であった湘桂作戦の進行とともに拡大強化されていったのでした。 一人一人の兵士が人間性を破壊されてゆくことと、その一人一人の兵士が加害者となってゆくこととは戦場では一体化しており、そこにあの戦争を見つめる大事なことの一つがあると思っています。このことを私はこれまでの戦争体験を見つめた自分の手記を何冊かの小型パンフに作ってきたことの中で分かったのです。 (2)大作戦で破壊された人間性湘桂作戦は十一月には柳州を占領し貴州省独山へと向かいます。これをやったのは十三師団で、すでに七ヶ月に及ぶ作戦であり兵隊には厭戦気分もつよまった時期でしたが、私はこの間三人の中国女性を強姦し、日本軍から逃げ去る住民に向かって発砲しています。中隊長などは若い女性に軍用外皮を着せ馬に乗せて連れ歩いていたこともあったが、その女性は或る日のこと人知れず山中で射殺されたとの話しが兵士間に流れたこともあります。十二月はじめ、一千五百キロ、七ヶ月の大作戦は終わって間もない頃、兵士仲間三人で徴発に出掛けた時のことです。私は部落裏山を登っている女性を目にし、この女性を追ったところを部落の武装民から発砲され左側胸部を撃たれたのです。幸い仲間が気づいて武装民に向け発砲してくれたので私は裏山を這いながら下り逃げたのですが、加害者としての罪の深さと今日の命の尊さが身にしみます。 戦後何年かすぎ戦争体験と向き合い、手記で書き綴るようになる頃まで、私は自分の負傷の経過を正直に他にもらすことはなくすぎていました。かくしたのは女性を追った事です。それをあからさまに出来るようになったのは、戦争での加害者としての自分の行動とその罪を自覚することができるようになり、日本の戦争が侵略戦争であったことも知り反省を深めさせられたからです。 私が知る限りでは、兵士仲間で自分の強姦を語ることはなかったと言えますが、強姦は多く作戦行動の際の「徴発」行動のなかで行われ、それは当時は軍の暗黙事だったのです。表向きは「徴発」は作戦中は日常的な行動で、私などには強姦を期待して部落への徴発に仲間と向かったことも度々です。「徴発」は主として軍隊生活に必要な物品の掠奪行為ですが、それのみでなく人権の尊厳を奪う行為でもありました。敵性地での戦争では全てを「お国のため」で通していたわけで、そこの中で人間性を守ると言うことは不可能だったと言えます。とくに日中戦争で日本軍によって行われた強姦の実状は全体として明らかにはなっていませんが、この人間の尊厳を踏みにじる行為に対し中国人が「獣兵」と呼び、徹底抗戦以外にはない戦争だったと語ったのを私は或る東京での集会できいたとき、重く深い思いに打たれたのでした。 (3)敗戦と天皇の軍隊と兵士一九四五年(昭和二〇)五月末、当時私の所属した師団は新占領地として警備の任に就いていた広西省西奥地を放棄して移動を開始したのです。兵士間には満州に行くらしいとの話しが流れていましたが、何故そんなところへとの軽い疑問はありましたが兵士は不問には馴れているし深くは考えなかったのです。戦後歴史家の本などで分かりましたが、この移動はアメリカ軍の沖縄本島上陸と言う状況の中で行われ、上海・南京方面への移動だったのです。師団は後方から重慶軍の追撃をうけながらも反転し、湘南省に入ったと思われる或る日の行軍中に、ソ連が仲介で講和が成立したとの部隊逓伝が流れたのに、宿営地では日本は負けたらしいとのひそひそ話しが交わされたのです。上級からは一言の話しもなくすぎて翌日の兵士は不安のまま行軍をつづけて四、五日後です。その日の宿営地で突然のように銃の菊花紋章を消せとの命令があったのです。それで日本は戦争に負けたのだと思ったのです。後日分かったところでは八月二〇日を二、三日すぎていた頃です。当時兵隊は日本がどんな状況下にあったかなど全く知りませんでしたし、行先どうなるのか不安の思いでしたが、そんななかでこれで死なずにすむと言う心の奥のよろこびのような感情が起きたのは忘れられないことの一つです。いま一つは、日本歴史上の重大事件である「無条件降伏」と言うことについては上級からの報告は一言もなかったことです。 嘘の部隊逓伝で戦争が終わったと知らせ、兵士には流言として敗戦をささやかせ、軍隊の「民」である兵士には重大事件である無条件降伏の事実(天皇放送など)も知らせぬままに、武装解除にそなえ天皇の権威を守るため銃の天皇家紋章を消さした、これが敗戦時の天皇の軍隊だったのです。 終戦翌年に復員したのですが無条件降伏と言う言葉は、上級からは一言の言葉もなかったままに終わったのです。満州では日本からの開拓民を放って関東軍首脳部は帰国したのと同様に、敗戦と言う重大事態に軍の「民」である兵士は見捨てられ動物的な体だけを燒土化した敗戦社会にもどされたのです。或る戦史家はそうした日本軍隊のことを「棄民の軍隊」だったと言っていたのを戦後に知り、成程そうだと思いました。 これは私の部隊だけのことだったのだろうかと思ったりもしましたが『インパール作戦敗軍行』(二〇〇〇年八月「本の泉社」)によると兵士は住民村長から「日本は負けた」ときかされて知ったと言うことですので、敗戦の正式報告を受けてない部隊兵士は他にもあったのだと思います。 従来のパンフにも述べたことですが十月二日の武装解除直前の私は中国住民から徴発して持っていた私物の砂糖を処分するため中国人に売りつけようとして、中国人数名に囲まれ、危ないところを助かったことがあったのです。 この時の私の行動はどういう事を語っているものなのか。当時の私自身は何らの違和感もなかった程に、「徴発」(略奪)は当たり前で兵士としての体質的なものになっていたのだと思いますが、それは侵略戦争の本質的な性格が兵士を通じて体現された行動だったのです。それにしても敗戦国の兵士である自分の立場をどのように受止め理解していたのかに大きな問題点もあったのです。戦争の終わったことは実感として受止めたが「敗戦」と言うことは頭では分かっても実感としては分からず言葉以上には受止めていなかったと言えます。それは兵士は沖縄戦も内地の空襲もソ連参戦も原爆も全く分からなかったし「無条件降伏」についての上部からの報告も一言もなかったと言う状況のなかで「敗戦」の実感がなかったのは当然だったのです。ですから間もなく武装解除が終わり、身につけていた武装がなくなり急に体が軽くなった瞬間には一種の解放感すら覚えたりしていたのです。 これは感覚的なものでしたが、これで戦争からも軍隊からも「解放」されたと言う気持に見舞われたのは印象的だったのです。いま考えると、武器がなくなったとき、そこには戦争とは反対の平和が見えたと言うことには、一兵士の体験ではあるが重要な意味があったと思います。それは憲法九条の二項にも通じていたからです。 いま一つ考えられることは、武器が取り上げられて丸腰になった後だったら私の行動はなかったのではと言うことです。私物砂糖は分からぬように投げ捨てたろうと思います。一兵士として武装していたから行動をする気にもなったと思うのです。略奪した砂糖を売りつけて金に替えようとした二重の略奪行動の背景には身につけた武器があったと言う体験にも憲法九条の持つ価値に通じるものを考えさせられます。 更にいま一つ私の行動の中には、明治以来の中で強化されたアジア民族への蔑視感が底流としてあったことです。朝鮮人を「半島人」と言い、中国人を「チャンコロ」と呼んでいた蔑視感です。そして敗戦後二ヶ月近くすぎて武装解除の場所に入ったと言うのに、私自身は侵略戦争に従軍し掠奪や強姦を重ねた一兵士のまま何ら変わってはいなかったのだということだったのです。 (4)「忠君愛国」の思想で流した涙一九四六年(昭和二一)六月四日、復員の上陸地は鹿児島で、ここで全国の都市が空襲で壊滅状態になっており、とくに日立市の災害図を見て大きな驚きを受けています。それまで私のみならず部隊兵士は、日本が空襲にさらされていたとは知らなかったのです。更に沖縄戦のことも分からずに居たのですし、敗戦とは知ってもその状況については何にも知らずに居たのです。復員解散式が行われ半分は無我夢中で復員列車で運ばれる途中のこと、広島に大変な爆弾が落ちたそうだとのことは中国での捕虜抑留生活中に耳にはさんだ程度にはきいていたその広島駅に停車したのは真昼間で、一面焼野原の情景を見て驚いたのです。しかしその悲惨さがいかなるものかを知るのは後日になってですが、この時の広島の情景はいまだに目に残っています。 列車が東京に着いたのは翌日の午後の早い頃かも知れませんが、上野となればやっと帰ったような気持と同時に、その首都東京が廃都となっている姿には、敗戦を直かに見た思いではじめて呆然とした悲しい感情に引きこまれたのです。上野常磐線ホームに立ってその情景を見ながら私の目が皇居の緑の森をとらえたとき、私の心は天皇を意識していました。そして呆然とした落膽の気持に重ねて、天皇の心中を思いやっていたら自分でも気づかずに涙が流れていたのです。思わぬ涙をぬぐった私は、しばらくの時間の後、故郷の父の安否を思いながら列車に身をゆだねたのですが、これが上野での復員した私の姿だったのです。 私がこの自分の姿と天皇を思って流した涙について考えさせられたのは戦後もかなりおそくなってからでしたがその時気づいたことは、その折の私の頭には戦場で倒れた将兵のことも、日本軍によって生活を奪われた中国民衆のことも、そして獣兵となった自分のことも、更には焼トタンに住んでいた都民への思いやりも、それらは消え去っていたと言うことです。頭にあったのは天皇への思いやりのみであり、流した涙は天皇の「臣民」の一人としての涙でしかなかったのです。 いま戦後六〇年をすぎて当時をふりかえってみると、天皇があの十五年間にわたった侵略戦争に対し深いかかわりを持つ中心的な存在だったと言う考えは全くなかったことです。私の頭に浮かべられた天皇とは、小学校で教わったことのある、民の釜の煙りに心を使ったと言う仁徳天皇とか、安定した国・民のために佛教をあがめ憲法を定めた聖徳太子とかなどからの姿での神性化された存在だった気がします。特に天皇のことで印象づけられたのは、太平洋戦争の直前の頃に出版された亀井勝一郎の『聖徳太子』などによる天皇美学から受けた影響は大きかったようです。 私はかつて父が「天皇」制否定を言ったのを思い出したのは戦後だったのですが、その頃までは天皇像への私の心境は、自覚はなかったが変わりはなかったと言えます。「聖戦」は嘘と気づき戦争への疑問を抱いた時に「天皇」を意識しなかったのは以上のようなことからだと思います。日中戦争や太平洋戦争は天皇抜きでその本質はとらえられないわけで、私が戦争に疑問を持っても侵略戦争と考え付かずに終わったのは当然だったと現在は思っています。教育勅語と軍人勅諭によってつくり上げられた忠君愛国の思想がいかに日本人の心を縛っていたかを思うにつけても、あの戦争を正当視する「君が代」「日の丸」を教育現場に強制することに反対するのは当然のことです。 第三章 戦後六〇年の歩み(1)戦後社会の変化と進展の中で生家にもどっても父は働けない体で、長兄の働きだったし、それに義姉は長い病に伏せまだ若い娘の姪が一家を世話している状況で大変だったのです。食糧不足の問題は長兄が漁業船員であったので何とか手に入れていましたが、いも類を入れたりの食事です。復員した体を休めてはいたものの、敗戦直後の混沌とした心境でした。家の仕事があれば手伝うのが精一杯です。召集前に働いていたのは陸軍造兵廠だったので敗戦でなくなり、就職できずにいたのです。こうして一ヶ月もすぎた頃に或る文芸雑誌から、三木清と戸坂潤の両氏の獄死を知ったのです。何故だろうと暗い疑問にとらわれ、ことによると戦争と関係があったのかとは漠然と感じたものの原因は分からず終いで、間もなく忘れ去っていきました。 そんなことの外には、小学校の女教師が私の家の近くにあった立着板にビラを張っていて、それはストライキを知らせるビラなのを知り驚いたことがあり、日本も変わったと思ったことがあります。 日立に住む叔母と叔父(義理)の心配で日立にある関東配電(東京電力の前身)の火力発電所に働くようになったのは復員一年後です。その面接に会社側と同格で労働組合側代表が同席していたのにも社会の変わり様をびっくりして感じたものです。 こうして段々と周辺の変わり様が分かるようになった頃に、アンドレ・ジイドの『コンゴ紀行』を文庫本(訳本)で読んで感銘したのは、人間は思想と行動が一致することの大切さを述べていたことで、何となくそれだけが心に残ったのです。そして就職してから、そうした存在を共産党員だと言われている人の何人かに感じたりしたのです。それが当初は労働組合は縁が遠かったのが次第に近づくようになり党員の人とも仲良くなるきっかけになったのです。 労働組合に近づく中で私も変わり出し、とくに河上肇の『貧乏物語』は社会的開眼の第一歩となり高橋庄治の『ものの見方考え方』は、これまで考えたこともない新しい世界観と言うものに接してびっくりしたと言うのがその折の正直なところです。その頃私は本などは余り読まなかったのですが、以上の二冊は労働組合文庫にあったのです。 こうして戦後の変わり様のなかで私と言う人間も変わってゆき、自分の体験した戦争は中国への侵略戦争であったこととか、三木清や戸坂潤の獄死がこの戦争反対とかかわったことだったことも知ったのです。しかしその後に叔母夫婦の養女との結婚問題が起き、私は自分が決めた労働者としての階級制の生き方を棄て小市民生活としての安住世界に生きる人間に成ったのですが、その世界も階級矛盾の世界であることを知り、再び結婚前の自分の世界への道へともどったのです。それからの私は今日までの五〇年、大過なくその道を歩いてきたことは、恩ある叔父夫婦や残した子供達にはすまなかったとの気持はあったとしても、正しいことだったと思っています。社会の矛盾に正しく対応してゆくことで自分の生き方の道も其処にあったからです。 (2)戦争体験者としての自覚から私が戦争体験を労働者の力と出来たのは多分一九五二年(昭和二七)頃の茨城県の組合大会で、警職法反対を発言したなかで、共産党と言う名前を反対団体として入れたときのことです。そうしたことを発言すること自体が当時の組合でも勇気を必要としたのです。その時に私を前に押し出したのは、湘桂作戦終了直後の徴発の時の負傷の思い出です。一度はあの時に死んだかも知れない命なのだと気づいたら、平和のため反動とはたたかおうと言う気持が湧いたのでした。それは会社労務政策である反共との闘いでもあったのです。この時から一つの関所を越えた思いでしたが、侵略戦争反対、反動法反対、反共反対が一つとなったはじめての経験となりました。 戦後六〇年をすぎ政党の力関係上にも国民意識上にも「反共」には変化がありますが根強い底流がありこの克服の努力は今日でもつづいている問題です。 私はそのためにも専制主義的天皇制と侵略戦争に反対を貫いた日本共産党の役割と歴史を学ぶことは、今日の日本共産党を理解する上でも大事ですが、「靖国」問題などを巡る問題などを持出し、かつての軍国主義時代復活を思わせるような現職大臣発言などを封じてゆくためにも重要だと思います。 ここ十年間ぐらいに私は、自分の戦争体験を小型のパンフとして何冊か手記として綴っていますが、その柱は自分の加害者としての在りのままの証言ですが、気がついたことは自分の罪の自覚のことです。それは最初の頃は自分の行為を罪として認識していたに止まっていたことです。そのことに気づいたのは南京大虐殺事件六〇周年記念東京集会に参加して、被害者だった中国人の証言をきいてからです。苦しめた本人の自分のことは分かっても、苦しめられた中国人自身のことへの気持はなかったと言うことです。私の罪の認識・自覚には重要な問題点・弱点があったことに気づかせられたのです。それまでの自覚とは自分の良心を満足させるに止まっていたのではないかと言うことです。これで本当に加害者としての反省と言えるのか、本当の反省とは中国人の苦しみ・悲しみ、被害の実態を知りそのことへの罪の自覚が出発ではなかったかと知らされたのです。 この私の問題点に気づいた後、これまで中国人犠牲者が日本の謝罪と賠償を要求して、日本裁判を行っていることに、そのことは知り乍らも裁判がどうなのかには関心を持たずにいたことにも反省し、日本の支援団体への会員になったり援助額(カンパ)も送るようになったのです。裁判の状況は一、二審共に被害事実は認めての国家無答責と言う時代おくれの法理論で個別補償は否定しており、今后は各裁判共に高裁にかけられます。わずかではあっても、かつての戦争での加害者の一人として支援はつづけてゆくつもりです。 (3)故郷の戦没者墓碑巡回を終わって二〇〇五年(平成十七)八月、私は故郷である旧福島県石城郡江名町(現在はいわき市)の戦没者の墓を巡り歩いて、八六名の墓碑銘を一冊の小型パンフに記録した書籍を墓前に献供し終わることができました。私が最初に生家墓地のある江名墓所の戦没者墓碑を尋ね巡回したのは一九八六年(昭和六一)で、これをまとめ『鎮魂の記』と言うパンフにして墓前に献供したのですが、その外にも寺と墓所があり、その戦没者墓碑を巡回し『鎮魂の記(続)』としてまとめ墓前に献供できたのは二〇〇四年です。この二度目の巡回には、小学校同級生の協力も得たのです。 二〇〇五年(平成十七)に戦後六〇年をむかえ、二冊に別々となった故郷の戦没者を一冊のパンフにして記した『戦後六〇年をむかえて』(パンフ)には私の戦争体験記を小学生当時から戦後までを載せました。いま一つには全戦没者(八六名)の戦没地域別表を作って資料として附したのですが改めてあのアジア太平洋戦争が途方もない無謀な戦争であったことを心にしみて知ったのです(巻末資料参照)。小学高等科卒業時の男性同級生数は、わずかに三六名しかなかった小さな町なのに、戦没者は戦争の全地域に及んでいたからです。 さらに驚きを禁じ得なかったのは、戦後も平成十三年一月一日現在で、遺骨の帰らない戦没者が一〇〇万体も異国の山野に残っていることです。これは厚生労働省の調べによるものでこれも資料として附しました(巻末資料参照)。 こうした事実に向き合うと、あの戦争は正しかったと宣伝する「靖国」史観や麻生外務大臣の戦争正当発言は許すことが出来ないし心の底から怒りが湧きます。 二十年来だった自分の念願の故郷の戦没者墓碑巡回が終わって間もない八月下旬、戦後六〇年での戦災展がある神峯公園の下にある市立郷土博物館を訪れました。日立市は戦争中三度にわたる災害を受けています。それで戦後の節目の年には「戦争と災害展」を催していたのです。そのことは何時頃からかは知っていても私は特に関心もなく、と言うよりは軽視していたのです。 戦後四〇年(一九八五年)八月には閣僚の靖国神社参拝問題で中曽根首相が「公式参拝」を強行した年で、そんなこともあって私ははじめて「戦争と災害展」を見に行ったのです。大したことないのだろうと思って行った私は、思い上がりに近い自分の不明を内心はじたのです。参観者への栞の「開催にあたって」の中では日中戦争を「侵略戦争」とはっきりのべていたし、開催目的を「平和と民主主義をいっそう確かなものにしてゆく」ためと記していたのです。特に私が感心したのは写真展示の中の二枚で、一枚は戦争への道が言論弾圧を経て進められたと言うもの、他の一枚は道端に土下座している数人の中国人を日本兵数人が蔑視の笑いを投げながら歩いているものでした。展示資料中には「陣中日誌」まであり、その説明には日本国内では満州馬賊とか匪賊とか呼んでいた中国人を「抗日勢力」と記していたのです。 つまり戦後の歴史学と歴史事実に沿って日立の戦災を見つめていたし、中曽根首相の靖国神社参拝強行の政治路線には反する内容のものだったのです。 その後一〇年をすぎた戦後五〇年の「戦争と空襲展」にも行きました。前回より立派な栞が渡されました。「開催にあたって」では戦争と戦災の体験が風化しつあることを心配する記が前回と変わっていたことです。「戦争への道」では満州への侵略戦争と記してある点は同じだが国内のことは表面的でした。そのかわり「ドイツのポーランド侵略」と記して三国同盟にふれこれが太平洋戦争を導いたとふれていた点は視点としては正しいと思いました。 写真展示では、前回私が感心した二枚の写真はなくなっていて、日中戦争への視点や国内の弾圧などへの光は消えていたのと、驚いたのは大東亜戦争美化の書籍が一〇冊も室内の処々に展示されていたことです。ここに私は国会決議(戦後五〇年の)で侵略戦争を国際的歴史にすりかえた政治動向の反映が現れたと思い、前回にはない侵略戦争美化への道に近寄った内容を感じたのです。 こうして戦後六〇年にはと内心危惧も抱いて行って驚いたことには参観者には案内栞もないし、展示室もなくなって、戦時中の写真が館内の壁に二〇枚ほど申訳程度に張ってあるだけだったのです。私は戦後六〇年でむかえている憲法第九条の危機を思いながら博物館を出たのです。体力も後退した年齢でどう歩けるのかと自己問答しながらです。 (4)悔いのない晩生に向かって八六年の生涯をふりかえるとそれなりの曲折のあった人生であったと言えますが、自らの意志ではなく兵士としてもすごした戦争の時期は、私の心に大きな傷跡を残したのです。そしてそれは同時に戦後を歩む原点でもあったのです。こうして今の私は、戦争を告発してゆくに止まらず、憲法改悪阻止に向かって行かなければとの問題意識を持たざるを得なくなってきています。そのことがこれまでのしめくくりにふさわしい晩生に向かっての態度であると思ってきたからです。 米軍再編に組込まれた国内の軍事体制もますます強化されています。最近では茨城の百里基地にも米軍機F15を配備しようとしており、反対県民集会も行われました。体力上参加はできない私は居住団地内にポスターを張りましたが、日本共産党日立金沢後援会のニュース(一月二六日)で「靖国神社が日立にやって来た」と言う記事を読み、昨年八月の郷土博物館での「戦災展」問題(第三章(3)に記)と共に、憲法改悪と戦争美化の動向が身近に行われていたことを知ったのです。 いま私は「満州事変」が起きた前後には帝国在郷軍人会によって排外主義と軍国主義の宣伝が、故郷の小さな町でも住民対象に行われたことを思い浮かべていますが、これがあの十五年間に及んだアジア・太平洋戦争に国民が欺かされた出発時の背景です。それと似たようなことが今日身近に行われていたのです。そのことを戦争体験者である私自身が知らずに居たと言うことを反省させられると共に、日立市内の民主的団体がどう受止めたのかについても気になったことでしたが、日立市の三月定例議会で日本共産党市議団が取上げるとのニュース(№一〇〇号)を見て、力づけられ心の内で喝采しました。かつて非公然活動を余儀なくされた戦前、日本共産党は一九二七年初めに「無産者新聞」社説(二月二六日)で、当時中国への軍事干渉と侵略準備を露骨にすすめていた日本帝国主義に対し「即時撤兵」を要求し「対支非干渉同盟」の結成をよびかけた(『日本共産党の六〇年』より)のは「満州事変」の四年前です。米軍再編で国内基地強化をすすめている中で、あの侵略戦争を正当視する宣伝体の「靖国神社」参拝を続ける小泉首相が着手した憲法改悪が急速化しこれを阻止する「九条の会」が全国に拡がりつつある今日のたたかいは、こうした歴史からも学んでゆくことが大事なのだと思います。 そう思って自己を見つめると、憲法を心をこめて勉強していないことを反省させられていますし、今年一月に不破前議長の「日中会談報告」をビデオできく機会があって大きく勉強になり自分の気持もはげまされたことがあって、健康保持につとめながら一歩でも周囲に入ってゆくためには日本共産党綱領を真剣になって学習することの重要性を、おくればせ乍ら、感じているところです。 今年は戦後六一年目になりますが、そのなかで私が体験した戦争とは何だったのかと言う問題について目覚めてから、自分の戦争体験と向き合うようになったのは今から二五年位前と思います。いまふりかえって一つの教訓と言えることは、何と言っても平和の尊さです。小さな生まれ故郷での戦没者墓碑銘を一人一人訪れたのは昨年(戦後六〇年)でしたが、小学同級生で戦没した或る人の甥と言う方から手紙が来て、そのなかに「叔父は国に殺されたのだと思っています」との言葉がありました。 私はドキッとしましたが、まさにあの戦争は日本国政府によって起こされ拡大されていった戦争だったのです。そのためにどれ程多くの命が国内、国外で奪われたことか。このことの深い反省から二度と戦争する国にはならないとの決意でつくられたその中心である第九条二項をゼロにする憲法改悪を急行させながら、憲法前文の平和主義の基本は変えるわけではないのだと、矛盾した言葉で国民を欺こうとしていますが、かつて侵略戦争を「東洋平和」確立の「聖戦」と国民を欺いたのと同じ手法です(資料№5を参照)。 私の晩生はいつまであるのか分からないけれど、悔いのない晩生に向かって、一日一日を大切に過ごして行けたらと思っています。 あとがき
しかし今回は自分の戦争体験に少しでも深く立入って今日の立場からも考え、一歩前へ進んでゆけたらとのつもりでしたが、仲々そうはゆかないで終わった思いです。 あの戦争が侵略戦争であり、その兵士としての私は加害者でもあったと言うことを分かったのは、戦争が内外の被害をもたらした後だったのでした。この残された教訓は忘れられません。 支配層が欺けるのは、国民の多数が欺きを見破れない場合ですし、何故見破れなかったのかと言うことは更に過去の歴史にも学び乍ら追求すべき問題のように思っています。それは憲法改悪を阻止する闘いのためにも重要な問題だと思います。欺く側には国民に知られてはならぬキーポイントを持っていて、それを国民の多数が見破れずに終わったのがあの戦争だったからです。 自分の体験をかえりみても、二度とこの轍をふんではならないとの思いで一杯です。この思いを手記とした私の戦争体験を綴った何冊かの小型パンフは次の通りですが、贈呈した団体や個人はその時々で同じではありませんでしたので、そのことを附しこれまでの永く厚い友宜に感謝しつつ、今回の一冊を贈呈さして頂きます。 |
|
日本共産党「赤旗」や『文化評論』、『民主文学』への投稿によるものから。 生家のある江名の戦没者墓碑を訪ね、その戦場追跡を記したもの。 小学生時代から復員帰国までの、侵略戦争時期の体験を追ったものである。 戦場と戦争の事実と真実への追究記。 旧日本陸軍史上最大の作戦参加のもの。 幼小年時期から戦後での戦争にかかわる思い出のものである。 生家のある江名以外の故郷の戦没者墓碑を訪ね、その戦場追跡を記したもの。 故郷(旧福島県石城郡江名町)の八六人の戦没者墓碑銘と私(佐藤)の戦争体験記を載せた一冊であり、戦没者墓碑を巡回して墓前に献供したものである。 |
〈資料〉
|
|||
(1) 十五年戦争のあしあとⅠ |
|||
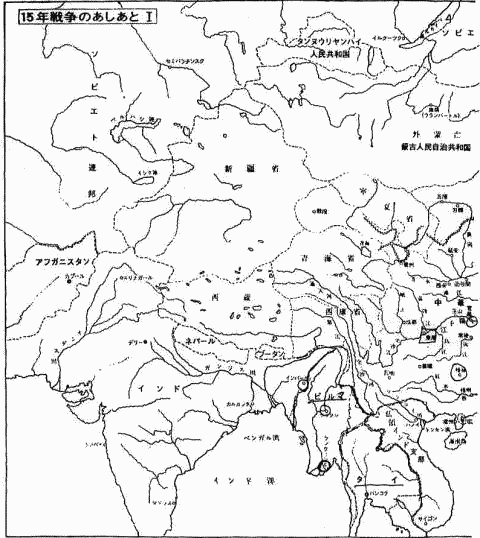 |
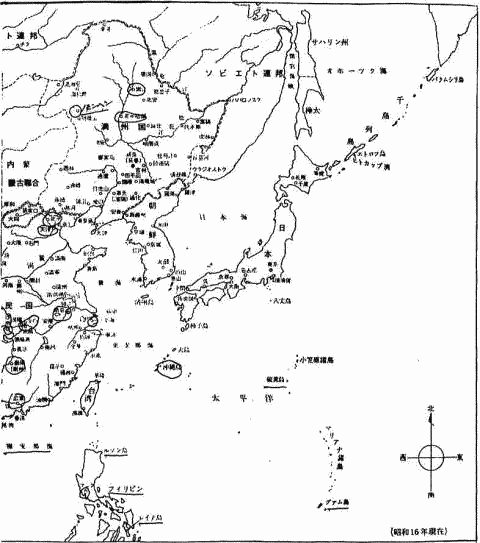 |
||
(2) 十五年戦争のあしあとⅡ |
|||
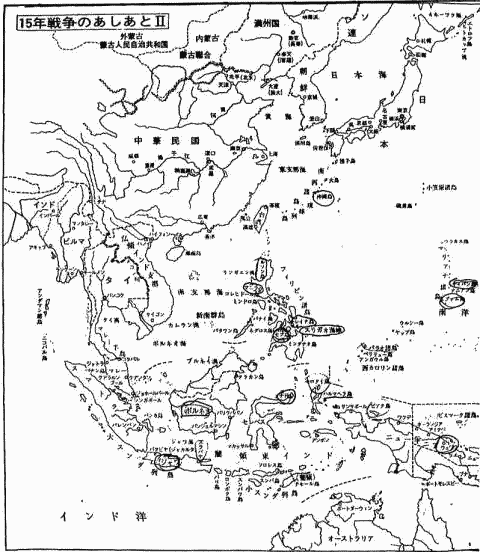 |
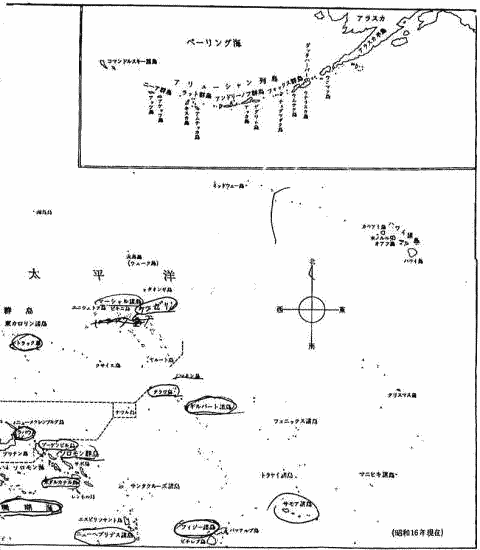 |
||
|
|||
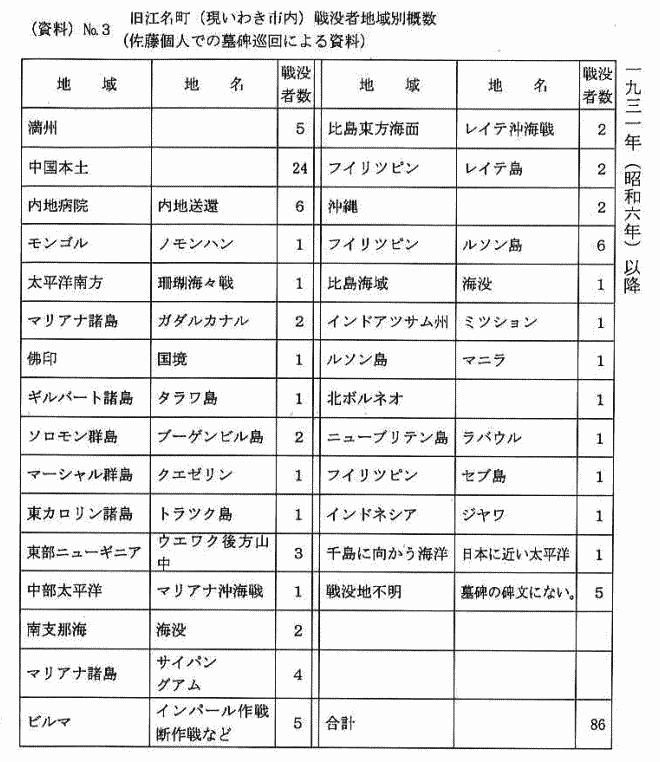 |
|||
|
|||
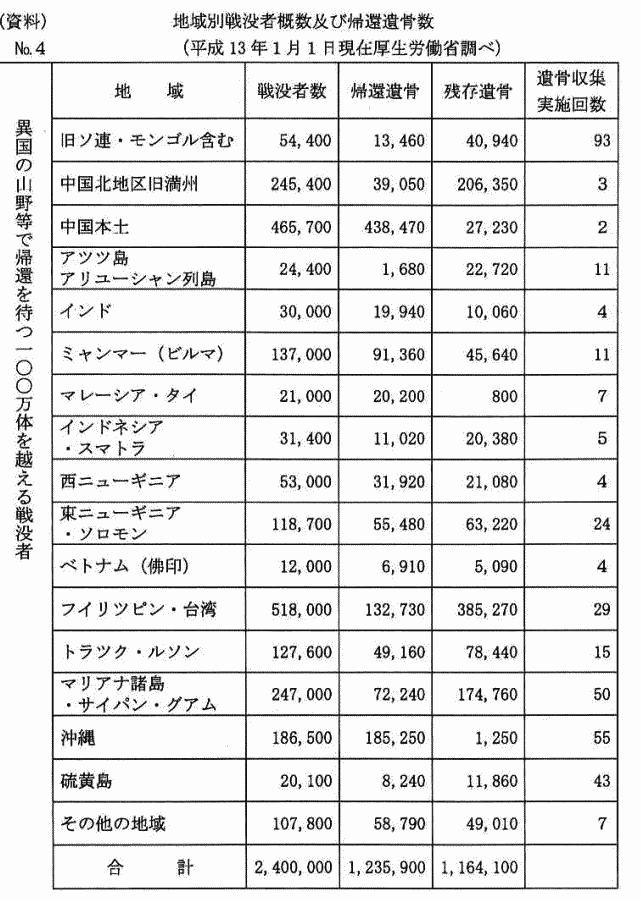 |
|||
|
|||
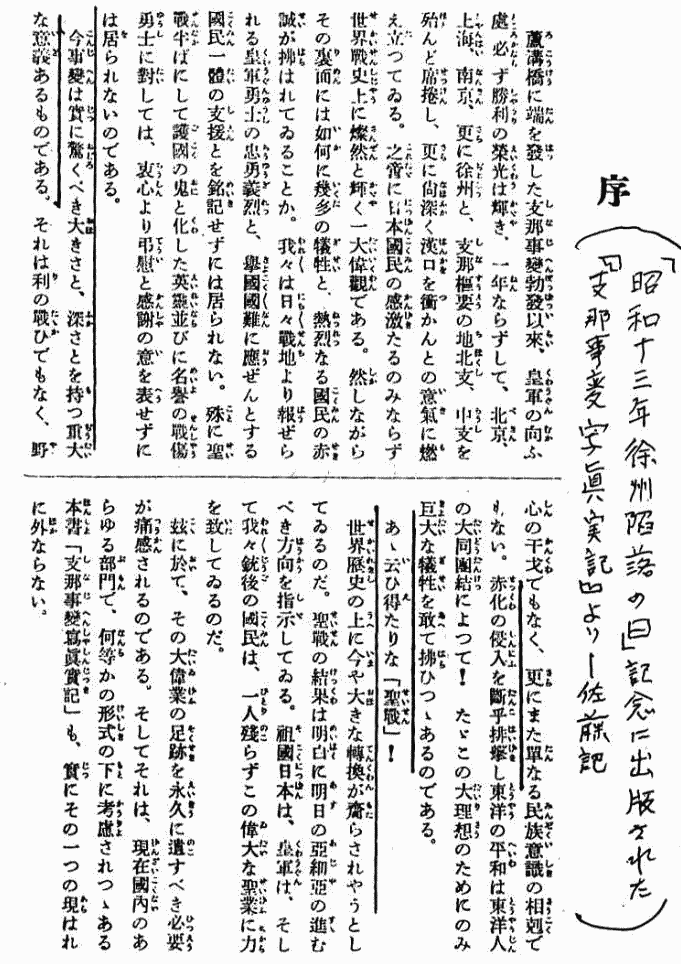
|
|||